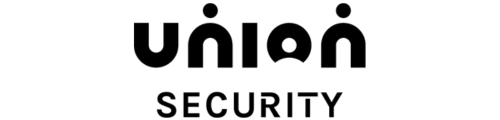近年、企業や施設、店舗、そして個人宅においても、防犯対策の重要性はますます高まっています。その中で注目されているのが「機械警備」です。人が常駐する警備とは異なり、センサーやカメラなどの機器を活用して24時間体制で監視し、異常があれば即座に対応する仕組みは、コストと安全性の両立を可能にします。
1️⃣ 機械警備の基本
機械警備とは、建物や敷地に設置した各種センサーや監視カメラが、侵入や火災などの異常を検知すると、自動的に警備会社の管制センターへ通報し、必要に応じて警備員が現場へ急行するシステムです。この仕組みにより、「常時監視」と「迅速な初動対応」を両立できます。
2️⃣ 仕組みと運用の流れ
機械警備は、「異常を検知する機器」+「それを監視・判断する管制センター」+「現場対応を行う警備員」の3つが連携して成り立っています。導入後の運用は、以下のような流れで進みます。

📍 センサー設置
施設の出入口、窓、金庫室、重要設備などに、侵入検知センサーや開閉センサー、ガラス破壊センサー、熱感知器などを設置します。屋外には赤外線ビームや超音波センサーを配置し、敷地外周の侵入も検知できるようにします。
🚨 異常検知
センサーが不審な動きや異常な温度変化、衝撃などを感知すると、即座に信号を送信します。近年はAIカメラによる画像解析も進化し、人や車両、小動物を識別して誤報を減らすことが可能になっています。
📡 自動通報
検知信号は通信回線を通じて警備会社の管制センターに送られます。センサーの種類や検知内容に応じて、映像確認や音声警告を行い、必要に応じて現場対応を手配します。
🚓 現場急行
警備員が最短ルートで現場へ向かいます。警備業法では25分以内の到着が求められますが、地域密着型の警備会社ではさらに短時間での到着を目指しています。
📝 初期対応と報告
現場で状況を確認し、必要に応じて警察や消防に通報。その後、対応内容や発生状況を報告書としてまとめ、再発防止策の提案につなげます。
3️⃣ 使用される主な機器
機械警備で使われる機器は、防犯・防災・監視・入退室管理の4つのカテゴリに分けられます。
🔒 防犯系機器
不正侵入や破壊行為を検知するための機器です。代表的なものに、窓やドアの開閉を感知するマグネットスイッチ、ガラス破壊時の振動や音を検知するガラス破壊センサー、屋外で赤外線ビームを遮断すると作動する赤外線ビームセンサーがあります。室内では、人体の熱や動きを感知する赤外線センサーや超音波センサーが有効です。金庫や重要書類保管庫には金庫センサーを設置し、不正開錠や移動を検知します。
🔥 防災系機器
火災やガス漏れなどの災害を早期に発見するための機器です。急激な温度上昇を検知する熱感知器、煙の濃度変化を検知する煙感知器、炎の赤外線や紫外線を感知する炎感知器、可燃性ガスや有毒ガスを検知するガス漏れ感知器などがあります。
🎥 監視系機器
防犯カメラや録画装置がこれにあたります。最近ではAI解析機能を備えたカメラが普及し、人・車両・動物を識別して誤報を減らすことが可能になっています。クラウド型カメラは遠隔地からの映像確認や録画保存ができ、複数拠点の一括管理にも適しています。威嚇や周囲への警告には防犯ベルやフラッシュライトも併用されます。
🚪 入退室管理系機器
電気錠やICカードリーダー、生体認証システムなどが該当します。誰がいつ出入りしたかを記録でき、内部不正の抑止にもつながります。
4️⃣ メリット
機械警備の最大の魅力は、人件費を抑えながらも高い防犯・防災効果を発揮できる点です。常駐警備員を減らすことでコストを削減でき、小規模店舗では月数千円〜数万円程度で導入可能なケースもあります。また、センサーやカメラは24時間365日稼働し、夜間や休日も休むことなく監視を続けます。
異常を検知すると即座に管制センターへ通報され、現場到着までの時間を短縮できます。さらに、映像やセンサーログが残るため、万一の際には証拠として活用でき、保険申請や警察への提出にも役立ちます。特定エリアだけを重点的に監視することも可能で、金庫室や研究室などの重要区画を強化できます。加えて、人が立ち入りにくい高温・低温・暗所などの危険区域も監視できるため、安全管理の幅が広がるのも大きな利点です。
5️⃣ デメリットと注意点
誤報の可能性:小動物や風、雨、太陽光の反射などでセンサーが反応する場合があります。近年はAI解析や感度調整で軽減できますが、完全にゼロにはできません。
エリア制限:警備業法では、異常発生から25分以内に駆けつけ可能な範囲に基地局が必要とされています。
異常検知のみ:実際の現場対応は警備員が行うため、契約内容によっては別途費用が発生します。
メンテナンスの必要性:機器の故障や停電、施設レイアウトの変更時には再設定や修理が必要です。
初期費用・ランニングコスト:機器購入・設置費用に加え、通信・保守費用がかかります。
6️⃣ 導入の流れ
機械警備の導入は、単に機器を設置するだけではなく、現場環境や利用目的に合わせた最適化プロセスが必要です。

🔍 現地調査とリスク分析
建物の構造や立地、周辺環境、利用時間帯などを確認し、侵入経路や火災リスクを洗い出します。例えば、夜間無人になる工場では外周センサーを重点的に配置し、昼間も人の出入りが多い店舗では入退室管理を強化します。
📑 プラン・見積作成
複数の機器構成案を提示し、費用と効果を比較します。この段階で、将来的な拡張や他システムとの連携も視野に入れます。
✍️ 契約
サービス内容、対応範囲、費用、駆けつけ時間、メンテナンス条件などを明確にします。
🔌 設置工事
機器の設置とシステム設定を行います。配線や通信環境の整備もこの段階で実施します。
📖 運用開始・操作説明
利用者に操作方法や注意点を説明し、誤操作や誤報を防ぎます。緊急時の対応フローも共有しておくと安心です。
🛠 定期点検・メンテナンス
機器の動作確認やソフトウェア更新を行い、常に万全の状態を保ちます。施設のレイアウト変更や増築があった場合は、機器の位置や設定を見直す必要があります。
7️⃣ サービス選びのポイント
機械警備は、導入する会社によって効果が大きく変わります。選定時には、以下のポイントを確認しましょう。
- 業種・施設特性に合った提案力:倉庫なら侵入検知重視、学校なら安全管理重視など、施設ごとの課題に合わせたプランを提示できるか。
- 駆けつけ体制の迅速さ:実際の到着時間や地域密着度を確認。地元に拠点がある会社は有利です。
- メンテナンス体制の充実度:故障時の対応スピードや代替機の有無、定期点検の頻度など。
- 最新技術への対応力:AI解析やクラウド監視など、新しい技術を積極的に取り入れているか。
8️⃣ まとめ ― 機械と人の融合が鍵
機械警備は、最新のセンサーや通信技術を活用し、効率的かつ高精度な防犯・防災を実現します。しかし、最終的な安心感を支えるのは、異常時に駆けつける人の存在です。「機械の正確さ」と「人の判断力」を組み合わせることで、真の安全が確保されます。
導入を検討する際は、機器の性能だけでなく、運用体制や対応力まで含めて総合的に判断することが重要です。
9️⃣ 広島で機械警備を導入するなら
広島・呉・東広島エリアで機械警備や防犯カメラの導入をお考えなら、ユニオンセキュリティ/SATがおすすめです。地域密着の提案力と、24時間体制の迅速な駆けつけ対応で、学校・工場・店舗・住宅など、あらゆる現場に「ちょうどええ安心」をお届けします。

- 地域密着の提案力:広島の現場感を熟知し、施設特性に合わせた過不足のない防犯プランを提案。
- 迅速対応:異常時には最短ルートで現場へ急行。夜間や休日も管制センターと連携し迅速に復旧。
- 防犯+αの活用提案:防犯カメラを業務改善や安全管理にも活用。
- 豊富な実績:広島県内で年間1,000台以上の防犯カメラ設置実績。
防犯・防災の強化をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. 機械警備と常駐警備はどう違うのですか?
A. 常駐警備は警備員が現地に常時滞在し、巡回や入退室管理を行います。一方、機械警備はセンサーやカメラで異常を検知し、必要時のみ警備員が駆けつけます。コスト効率を重視する場合は機械警備、常時の人的対応が必要な場合は常駐警備が適しています。
Q2. 誤報はどのくらいありますか?
A. 小動物や天候などで誤作動する場合がありますが、近年はAIカメラや感度調整により大幅に低減しています。設置環境に合わせた機器選定とチューニングで、不要な発報を最小限に抑えられます。
Q3. 導入までの期間はどれくらいですか?
A. 小規模施設であれば、現地調査から設置完了まで最短1〜2週間程度が目安です。規模や機器構成によって変動しますが、事前の打ち合わせでスケジュールを明確にします。
Q4. 機械警備だけで十分ですか?
A. 多くのケースで十分な防犯効果がありますが、施設の性質やリスクによっては常駐警備や巡回警備との併用が望ましい場合もあります。リスク分析に基づいたハイブリッド運用が効果的です。
Q5. 広島県外でも対応できますか?
A. ユニオンセキュリティSATは広島県内を中心に活動していますが、提携ネットワークを活用し、近隣エリアにも対応可能です。詳細はご相談ください。
この記事の制作者

粂井 友和
システム警備を提供して20年以上、お悩みを解決したお客様5,000件以上のSATで責任者を務めています。
防犯カメラや防犯センサーなどを活用した防犯システムを、様々な状況に適した形でご提案します。
お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。